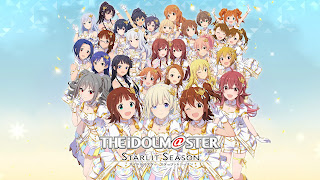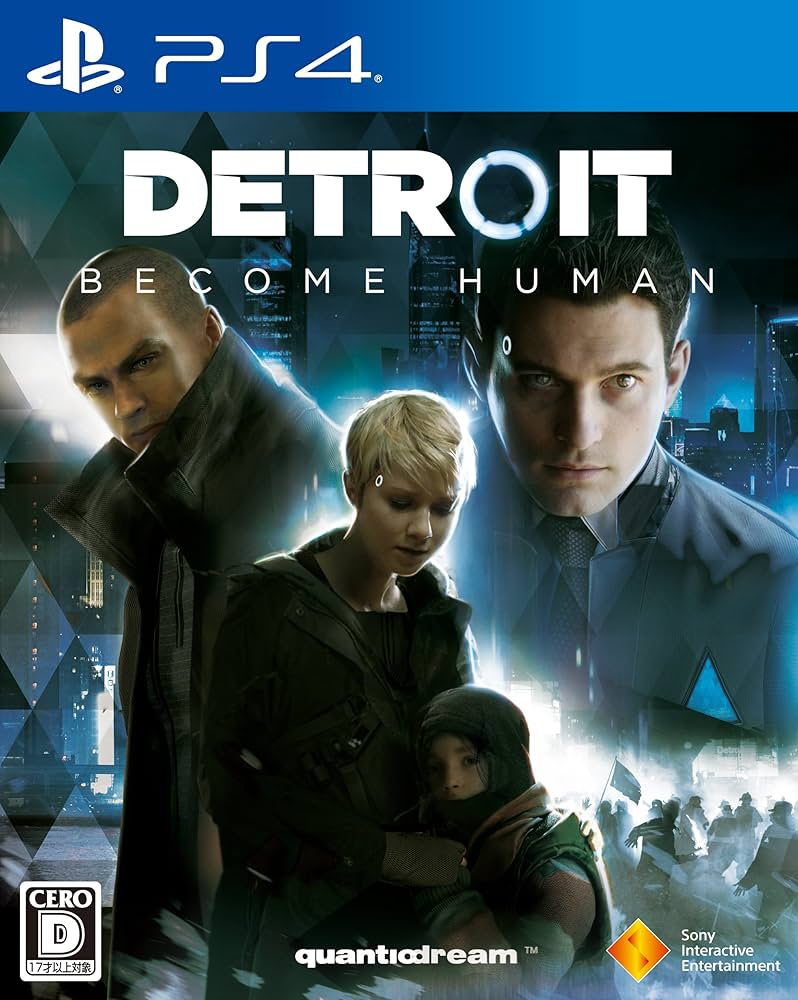ゲーム制作って、とにかく集中する作業ですよね。僕も作っていると、どんどんのめり込んでいきます。でも、最近ふと思ったんです。それって、ある意味「危険」なことかもしれないなって。
というのも、自分が作っているものを客観的に見る視点が、どんどん失われていくからです。これはたぶん、多くのゲーム開発者にも当てはまることだと思います。自分の作品に熱中するあまり、「自分のゲームを客観的に見れなくなる」。これは、開発者にとって結構深刻な問題かもしれません。
「客目線で見ろ」とよく言われますよね。たしか松下幸之助も、そういう考えを大切にしていたはずです。でも、開発者にとってこの「客観視」は、意外と落とし穴になることもあるんです。
ユーザーにとっては、そのゲームの「第一印象」がすべてです。初めて見るときのインパクトって、やっぱり重要なんですよね。でも、それを意識しながら作るのって本当に難しい。
だから僕は、なるべく常に「客観的な視点」を持とうと心がけています。ただし、他人の意見に流されすぎてもよくない。そのバランスが大事なんです。
客観的に見るというのは、つまり「自分を俯瞰する」ということです。自分のゲームも、制作の進め方も、時には自分の行動や考え方も。そうやって一歩引いた視点で見ることで、今まで見えなかったものが見えてくる。そこに、物事の本質が隠れていたりするんですよね。
ゲーム制作は情熱と集中が大事。でも同時に、自分の位置を冷静に見つめる「客観性」も、同じくらい大切だと僕は思います。